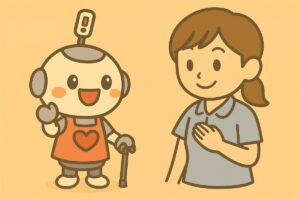👻「あんたもこっちにきんしゃい」──深夜に誰かと話す入居者
深夜2時すぎ。グループホームの見回りをしていた私は、しんと静まり返った廊下を歩いていた。
入居者は全員就寝済み。廊下は常夜灯の淡い光だけが照らし、私の足音がコツ、コツ、と小さく響く。

そんな中、不意に「誰かが話している」声が耳に入った。
最初はテレビのつけっぱなしでもあるのかと思ったが、違った。テレビの音ではない。
それは、まるで誰かに語りかけるような、柔らかい口調の“人の声”だった。
耳を澄ますと、その声は廊下の奥――Bさんの部屋からだった。
Bさんは80代後半の女性。少し認知症があるが、普段は穏やかで、夜中に声を出すような人ではない。
私はそっと近づき、扉の前に立って耳を澄ました。
「……風邪ひくよ、そんなとこおったら……もう遅いけぇ、布団入りんさい」
「うん、うん……そうじゃね……こっち来んさい」
誰かと会話しているようだった。でも、声はBさん一人分しか聞こえない。
私は軽くノックして、「失礼します」と声をかけながら、少しだけ扉を開けた。
部屋は暗く、常夜灯だけがぼんやりと灯っていた。
その薄明かりの中、Bさんはベッドを離れて、部屋の隅――壁と壁が交差する角の方向に立っていた。
腰を少し曲げ、誰かに語りかけるように、身振り手振りまで交えて何かを話していた。

「ほら、あったかいけぇ、こっちおいで……はよ寝なさい」
その声は、どこか懐かしさを感じるような、優しい響きだった。
しかし、彼女の視線の先には――誰もいない。
ただの壁と床の交差点。けれどその空間には、何か“気配”のようなものが漂っていた。
私は緊張をこらえながら声をかけた。
「Bさん、どうかされましたか? もう遅い時間ですので、そろそろお布団に戻りましょうか。」
するとBさんは、まるで私の存在に今気づいたかのように、ゆっくりとこちらを振り返った。
そして、にこりと微笑んで言った。
「ほら、あんたもこっちにきんしゃい。こっちはあったかいけぇ」
その言葉が、私に向けられたものなのか、それともまだ“そこ”にいる誰かに向けての言葉なのか、わからなかった。
私は静かに彼女に近づき、手を添えてベッドまで戻ってもらった。
布団をかけながら、何気なく尋ねた。
「さっき、どなたかとお話しされてましたか?」
するとBさんは、目を細めて天井を見ながらこうつぶやいた。
「最近、あそこに立っとる子がいるんよ……かわいそうにね、毎晩、じーっと見とるんよ……」
私は返す言葉を失い、ただ黙って彼女の額にそっと手を当てた。
熱はない。意識もはっきりしている。
けれど、あの角には確かに“何か”がいた。そんな気がしてならなかった。
その夜、私は何度もその部屋の前を通ったが、どうしても角を見ることができなかった。
あとがき
この出来事を記録に残すべきか悩んだが、介護という仕事に携わっていると、こうした「言葉では説明できない」ことに出くわすことがある。
もちろん、Bさんのような認知症を持つ方が、幻視や記憶の混乱によって“誰かが見える”と語ることは珍しくない。
脳の働きの乱れによって、本来は存在しない人物や風景を「実在するもの」として認識してしまうことがあるのだ。
けれど――私はあの夜、ただの幻には思えない“何か”を、確かに感じてしまった。
あの静かな部屋の角に漂っていた、説明のつかない気配。
Bさんの語る言葉の、あまりにも自然で、優しさに満ちた口調。
「視える」かどうかではなく、「確かに“そこ”にいた」ような確信。
私たち介護士は、医学や常識だけでは測れない現場に立っている。
だからこそ、あの夜のような出来事を、簡単に“症状”の一言で片づけてはいけないような気がしている。