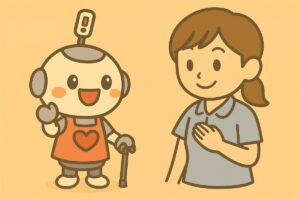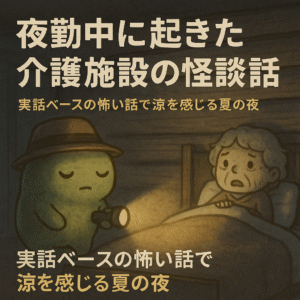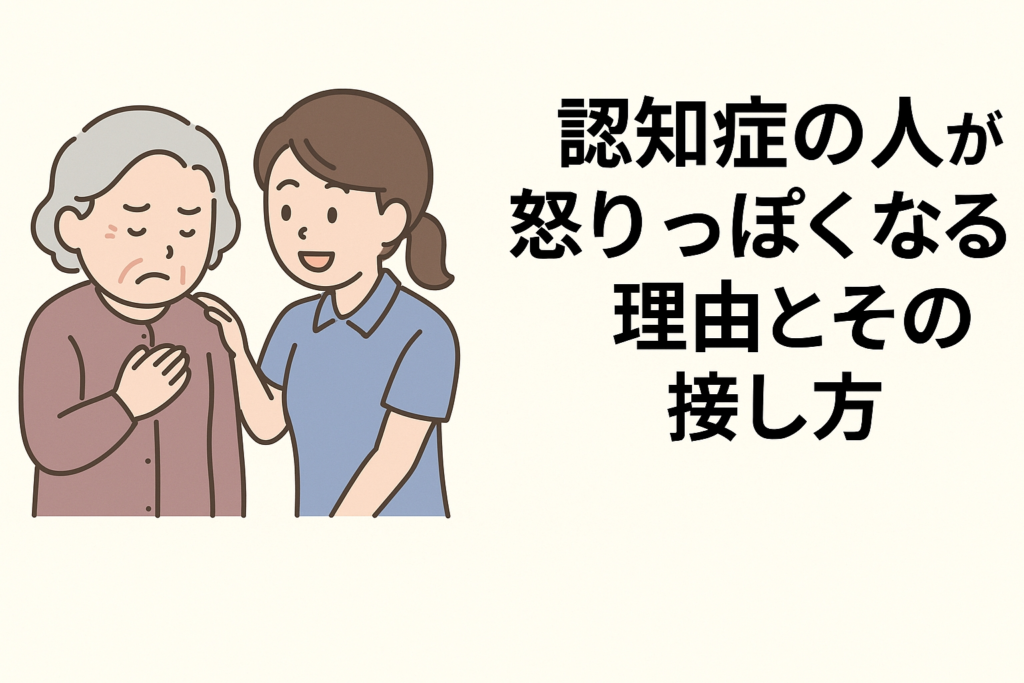
年齢を重ねるにつれ、誰しもが身体や心にさまざまな変化を感じるようになります。中でも認知症は、高齢者本人だけでなく、周囲の家族や介護職員にとっても大きな課題となります。特に、「怒りっぽくなる」「すぐに怒鳴る」「物に当たる」などの行動が見られると、対応に悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、認知症の方がなぜ怒りっぽくなってしまうのか、そしてどのように接することで本人の不安を和らげ、穏やかに過ごしてもらえるのかを、介護現場での実例や考え方を交えてご紹介します。
なぜ怒りっぽくなるのか?その背景にある心理とは
認知症になると、記憶力や判断力の低下、時間や場所の認識が曖昧になるなどの症状が現れます。これらの変化によって、日常生活の中で「自分が何をしていたか分からない」「知らない場所にいる気がする」「言いたいことがうまく伝わらない」といった“混乱”や“焦り”を頻繁に感じるようになります。
その結果、「怒り」として感情が表に出てしまうことがあるのです。
たとえば、
- 「自分の財布がない!」と怒る → 実際は置き忘れているだけ
- 「騙されてる!」と叫ぶ → 家族や職員の言動が理解できず、疑心暗鬼になる
- 「なんでそんなこと言うんだ!」と怒鳴る → 自尊心が傷つけられたと感じる
これは“認知症による障害”であり、わざと怒っているわけではありません。怒りの裏には「不安」「恐怖」「混乱」「悲しみ」など、複雑な感情が隠れています。

怒りの感情を悪化させないために気をつけたい接し方
認知症の方が怒ってしまった時、介護者ができる最も大切なことは「否定しない」「反論しない」「落ち着いて受け止める」ことです。
1. 否定しない
「そんなこと言わないで」「間違ってるよ」といった言葉は、認知症の方の自尊心を傷つけてしまうことがあります。「そうだったんですね」「不安でしたね」と共感する姿勢を持ちましょう。
2. 距離をとって見守る
激しい怒りが出た場合は、無理に言い聞かせようとせず、少し距離を取って落ち着くのを待ちます。感情が収まった頃に、安心する言葉や行動を心がけると効果的です。
3. 環境の見直しも重要
怒りの原因が「環境」にあることも少なくありません。
- 部屋が騒がしい
- 知らない人が多い
- 照明が暗くて不安
このような状況は混乱を引き起こしやすいため、できるだけ本人が落ち着ける環境を整えてあげることも大切です。
実際の介護現場での工夫と成功事例
介護の現場では、怒りっぽい利用者の方との接し方に悩むことが少なくありません。しかし、ほんの少しの工夫で状況が改善するケースもあります。
事例:Yさん(80代・女性)
Yさんは、日々「家に帰らなきゃ」と怒りながら施設内を歩き回る方でした。ある日、スタッフがYさんの故郷の話を聞いてみたところ、穏やかな表情に変わり、怒ることが減ったのです。
→ポイント:本人の「記憶にある世界」に寄り添うことで安心感が得られた
事例:Kさん(70代・男性)
食事時に毎回怒って配膳を拒否していたKさん。試しに昔使っていたような器でご飯を提供すると、驚くほど素直に受け取るようになりました。
→ポイント:視覚や触覚の「なじみ」が落ち着きをもたらす
このように、「その人らしさ」を大切にすることで、怒りの感情を和らげることができます。
まとめ|怒りの裏にある感情を見つめる
認知症の方の怒りには、必ず理由があります。その感情の裏にある“不安”や“戸惑い”に寄り添い、決して否定せず、落ち着いて関わることが大切です。
介護は、マニュアル通りにはいかないからこそ、日々の観察と心のやりとりが何よりも重要になります。怒りに隠れた「助けて」のサインを見逃さず、ひとつひとつ丁寧に向き合うことが、認知症ケアの第一歩です。