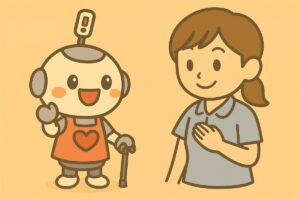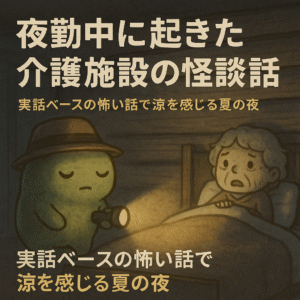高齢者の介護をしていると、「夜中に突然歩き回る」「どこかへ行こうとする」といった場面に出会うことがあります。これは“徘徊”と呼ばれる認知症の代表的な行動のひとつです。夜中の徘徊は、転倒や事故などのリスクだけでなく、介護者の精神的・身体的な負担にもつながります。
今回は、夜間の徘徊が起こる背景とその対処法について、介護職員の立場から具体的に解説していきます。
認知症による「夜間徘徊」とは
徘徊とは、本人の意思に関係なく目的もなく歩き回る行動を指します。ただし、本人にとっては“目的がある”ことも多く、「仕事に行かなくては」「子どもを迎えに行く」など、本人なりの理由で行動していることも少なくありません。
特に夜間の徘徊は、昼夜逆転や不安・混乱といった症状から起こることが多く、寝ていたはずの高齢者が深夜に起きて、外に出ようとしたり、施設内をうろうろしたりといったことが起きます。
なぜ夜中に歩き回るのか?主な原因とは
夜間の徘徊には、以下のような背景が考えられます。
- 昼夜逆転の生活リズム
認知症が進むと体内時計が乱れ、昼に眠って夜に覚醒するという昼夜逆転の傾向が強まります。その結果、夜中に活動を始めてしまうのです。 - 不安・混乱・見当識障害
自分がどこにいるのか、時間が何時なのかが分からなくなる“見当識障害”によって、「今すぐ家に帰らなきゃ」「仕事の時間だ」と勘違いしてしまうことがあります。 - トイレの失敗や不快感
夜中に尿意で目が覚めても、トイレの場所がわからず探し回った結果、徘徊につながることがあります。 - 習慣的行動の継続
昔の生活習慣が体に染みついていて、「毎朝4時に散歩に行っていた」など、過去の記憶の影響で自然に体が動いてしまうこともあります。
実際の現場での体験と対応策
私が介護職として働く中でも、夜中に施設内を歩き回る利用者様に出会うことは珍しくありません。あるご利用者様は、毎晩2時になると「もう朝だよ」と言って自室を出てしまい、玄関まで向かおうとします。
このようなとき、私たちスタッフは強く止めるのではなく、まずは声をかけて話を聞くことから始めます。
「どうしました?」「何か探しているのかな?」
安心してもらえるような声かけを心がけ、本人の“目的”を否定せず、「もう少しゆっくりしてから出かけましょう」と提案し、部屋に戻っていただくようにしています。

介護者ができる対応と工夫
徘徊を完全に止めることは難しいですが、次のような工夫で事故や混乱を防ぐことができます。
- 部屋に目印をつける:ドアやトイレに分かりやすいサインを設置し、場所がわからなくなるのを防ぐ。
- 照明の工夫:夜間は薄明かりをつけておき、転倒を防止しながら不安も軽減する。
- 日中の活動を意識的に増やす:散歩やレクリエーションなど、昼間にしっかり体を動かしてもらうことで、夜の睡眠の質を向上させる。
- 音が出るセンサーを設置する:部屋から出ようとしたときにアラームが鳴るようにすれば、介護者がすぐに対応できる。
- GPSの活用:外出してしまった場合に備え、位置情報がわかる端末を身につけてもらうのも有効です。
家族に伝えたい:怒らず、否定しない
ご家族にとっても、夜中に起き出して徘徊する親の姿はとても心配なものでしょう。しかし、本人に悪気があるわけではありません。否定したり怒ったりすると、かえって不安や混乱が増すことがあります。
できるだけ冷静に、「今は夜だから、少し休みましょう」「朝になったら一緒に行こう」といった言葉で、安心感を与えてあげることが大切です。
徘徊は「訴え」かもしれない
徘徊は、認知症の症状のひとつであると同時に、何かを訴えているサインでもあります。たとえば、「さびしい」「不安」「誰かに会いたい」など、ことばにできない想いが、行動として表れているのかもしれません。
私たち介護職はその背景をくみ取りながら、ただ“歩き回っている”のではなく、「何を感じているのか?」に心を寄せる姿勢が求められます。
最後に
夜間の徘徊にどう向き合うかは、介護現場でも永遠の課題のひとつです。完全に防ぐことは難しいものの、「なぜ歩き回るのか」「どう対応すれば安心してもらえるのか」を理解することで、少しずつ不安やトラブルを減らすことができます。
夜中に起きて歩く姿の裏には、必ず“理由”があります。私たちがその理由に耳を傾け、安心を届けられる存在でありたいものです。