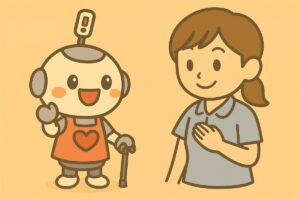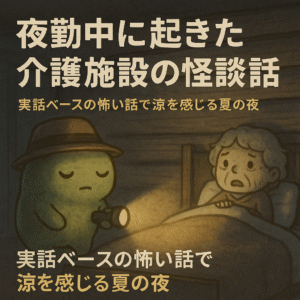2025年7月28日、厚生労働省が介護保険証(正式には「介護被保険者証」)の運用ルールの見直しを提案しました。 現在は65歳になると、要介護認定を受けていなくても全国の高齢者に一律で保険証が交付される仕組みです。しかし今後は、「要介護認定の申請時に交付する」運用への切り替えが検討されているとのこと。
このニュースを聞いて、正直なところ「本当に非効率が解消されるのだろうか?」と疑問に思いました。 私は現場で働く介護職員です。利用者さんやそのご家族が保険証をなくしてしまった時の対応や、申請時の混乱をこれまでに何度も経験してきました。 この変更が、私たち現場やご家族、本人にとって本当に“わかりやすい運用”になるのか?現場から見た視点で、考えてみたいと思います。
65歳になったら届く「青い保険証」
現在は、65歳の誕生日を迎えると、介護保険の被保険者証が自動的に自治体から郵送されます。 実際には使う機会がなく、しまい込まれたまま…という方も多いのが現実です。
私たち介護職員も、ご本人やご家族から「保険証がどこにあるかわからない」と言われ、書類が見つかるまで待たなければならなかったり、再交付を依頼したりといった手間が発生することはよくあります。
厚労省が今回挙げた「紛失が多い」「二度手間になる」という指摘も、現場感覚としては納得できます。 一方で、「申請時に初めて交付」という新たな運用に切り替えた場合、本当にこの混乱が減るのかは、少し疑問もあります。
提案されている見直しの中身
厚生労働省の案では、65歳到達時の一律交付はやめて、 「要介護認定の申請時」に保険証を交付する方式に切り替える、というもの。
これにより、
- 使わない人への無駄な交付がなくなる
- 紛失してしまう人が減る
- 自治体の発行作業・コストが減る
というメリットがあると説明されています。
さらに今後は、「介護情報基盤」と呼ばれる、オンラインで関係者が情報共有できる仕組みの構築も並行して進めるとのこと。 こうした“デジタル化の波”は、今の時代に沿った流れなのかもしれません。
現場から見た「不安」と「もやもや」
ただ、制度を見直したからといって、現場がすぐにスムーズになるとは限りません。
私がまず懸念するのは、「本人や家族が保険証を持っていない状態で申請を始める」ことで、逆に混乱を招かないか?という点です。
申請の際に必要なものが揃っていなかったり、書類のやり取りで時間がかかったりすると、ケアマネジャーや相談員、行政職員、そして私たち介護職員にも影響が出ます。
また、制度の変更がうまく周知されないままスタートしてしまうと、「今までは届いてたのに、どうして来ないの?」と混乱する高齢者や家族も出てくるでしょう。
本当に「非効率の解消」になるのか?
厚労省は「非効率の解消」を目的にこの見直しを打ち出していますが、 私は逆に、別の混乱が新たに生まれる可能性も感じています。
そもそも保険証の再発行は現在でも可能ですし、実際にそれほど大きな問題ではありません。 それよりも、「介護保険の存在を広く知ってもらう仕組み」や、「使いやすいサポート体制」のほうが、今の現場には必要なのでは?とも思ってしまいます。
デジタル化で効率化を図るという流れ自体は否定しません。 ただし、それが高齢者やその家族にとって本当に使いやすいものなのか? 制度設計の段階で、ぜひ現場の声も取り入れて考えてほしいと強く思います。
まとめ:制度変更の前に「声を聞くこと」を
介護保険証の一律交付の見直しは、たしかに合理的な面もあるでしょう。 しかし、実際に使う人、そのサポートをする人たちが混乱しないよう、丁寧な周知とサポートが不可欠です。
制度を効率化することと、現場の実情に寄り添うことは、必ずしも同じではありません。 そのギャップを埋めるのが、本来の“制度設計”だと思います。
現場の一介護職員として、こうした動きを注視しながら、日々の支援に向き合っていきたいと思います。