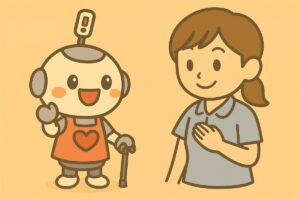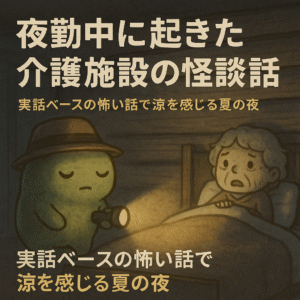「もうそろそろ、家に帰らんと…」
「こんなとこにおったらいけん。家に帰らせて…」
介護現場で働く人なら、一度は耳にしたことがある言葉ではないでしょうか。
認知症の方がよく口にするこの「帰りたい」という訴えは、単なる場所の移動願望ではなく、もっと深い“想い”が込められていることがあります。
今回は、そんな「家に帰りたい」に込められた意味と、介護職員としてどのように向き合い、対応すればよいのかを考えてみたいと思います。
「家に帰りたい」の本当の意味とは?
まず前提として、認知症の人が言う「家」とは、必ずしも現在の自宅を指しているとは限りません。
実家、若い頃に住んでいた場所、あるいは心の拠り所となる「記憶の中の家」…。
その人にとって、安心できる場所・自分の居場所と感じる空間を「家」と呼んでいることが多いのです。
また、「帰りたい」という訴えは、
- 環境の変化による不安
- 人間関係のストレス
- 体調不良や疲労
- 日課が乱れたことによる混乱
など、さまざまな心の不安や不満の現れとしても見られます。
つまり、「家に帰りたい」は“何かが不安”のサインであり、SOSでもあるのです。
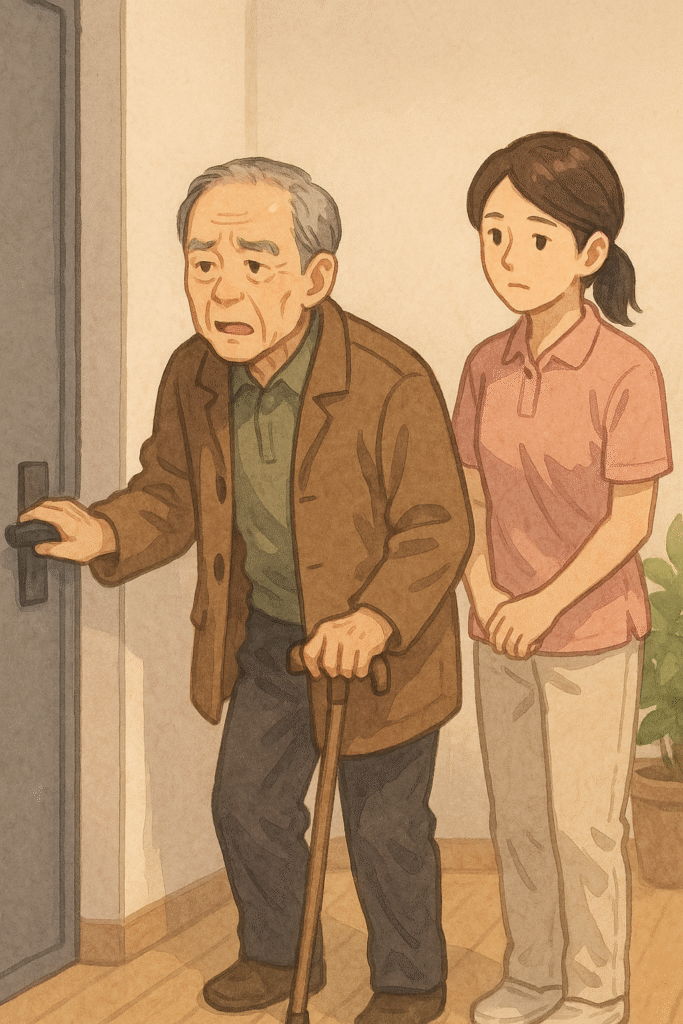
否定しない・叱らないのが鉄則
この訴えに対し、介護職員や家族がつい言ってしまいがちな言葉があります。
「ここがあなたの家よ」
「帰れるわけないでしょう!」
「もう亡くなった家なのに…」
このような“正論”は、認知症の方には通じません。むしろ混乱を深め、怒りや悲しみを呼び起こすことすらあります。
大切なのは、否定せずに気持ちに寄り添うことです。
「そうなんですね。帰りたい気持ち、分かります」
「どんなお家だったんですか?」
「お家で何をしてたんですか?」
こうした会話を通じて、本人の気持ちを受け止め、共感していく姿勢が求められます。
気持ちをそらす・環境を変える
とはいえ、四六時中「帰りたい」と言われると、職員や家族にとっても精神的な負担になります。
そんなときには、“そらす”ことも一つの方法です。
たとえば、
- 散歩やおやつの誘い
- テレビや音楽への誘導
- 折り紙や塗り絵などの作業
特に食事の時間帯や夕方は「帰宅願望」が強くなる傾向があります。
夕暮れ症候群(サンセット症候群)とも呼ばれ、この時間帯には静かで安心できる空間づくりが効果的です。
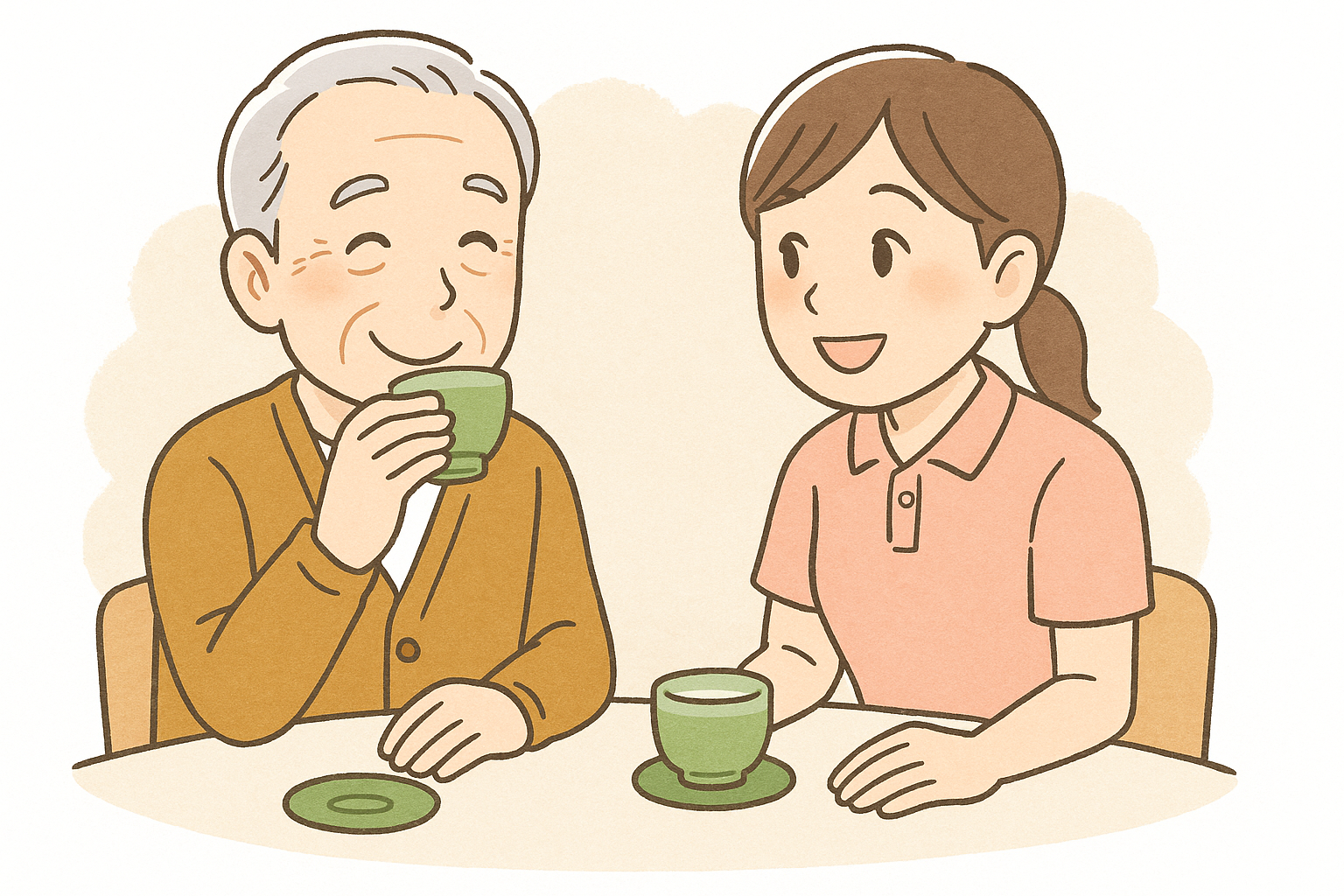
家族との連携も大切
「帰りたい」という訴えに対して、施設の職員だけで対応しきれない場面もあります。
そんなときには、ご家族の協力を得ることも大切です。
- 本人の安心できる言葉がけを聞いておく
- 本人の“家”のイメージや昔のエピソードを聞いておく
- 定期的な面会や手紙、ビデオメッセージの活用
職員と家族が連携し、本人の“安心のカギ”を共有していくことが、混乱を和らげる手助けになります。
介護者自身も心のケアを
何度も「帰りたい」と言われると、介護者自身も心がすり減ってしまいます。
「何度説明しても通じない」
「どうして分かってくれないの?」
そんなふうに感じてしまうのは、自然なことです。
大切なのは、「自分を責めないこと」。
本人の訴えは、あなたが悪いからではなく、病気の症状によるものです。
時には、他のスタッフに相談する。
外の空気を吸ってリフレッシュする。
小さな喜びを日々の中で見つける。
介護者自身が疲れすぎないことも、良い対応を続けるためには欠かせません。
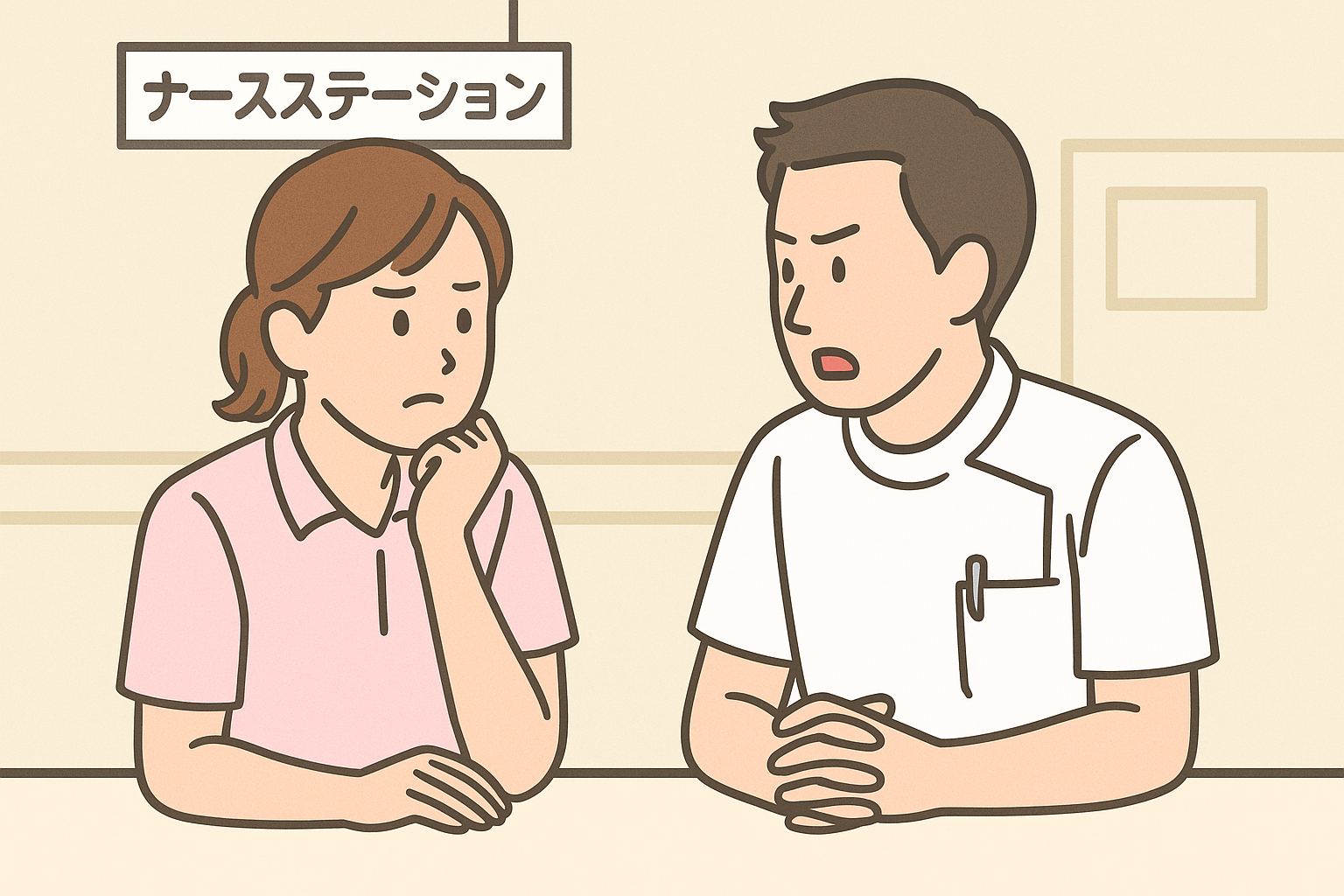
まとめ:「帰りたい」は“心の叫び”
認知症の人が「家に帰りたい」と言うとき、そこには“安心したい”“元の自分に戻りたい”という強い思いが込められています。
その言葉を頭ごなしに否定せず、心の奥にある気持ちを理解しようとすることが、真の寄り添いに繋がります。
介護はときに難しく、ときにやさしい。
「帰りたい」にも、そっと寄り添うやさしさを。
私たちにできることを、少しずつ、日々の中で探していきましょう。