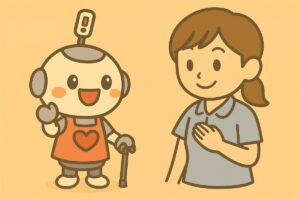静かな深夜の巡回
その夜の勤務は、いつも通り静かだった。
深夜のグループホーム。見回りを終えた私は、廊下の薄明かりを受けながら、静かにフロアを歩いていた。時刻は2時過ぎ。すべての利用者が眠りに就き、かすかないびきと時計の針の音だけが、夜の空間に浮かんでいた。

利用者Tさんとの再会
そんなとき、コールが鳴った。
表示を見ると、Tさんの部屋からだった。
Tさんは、80代半ばの女性。軽度の認知症があるものの、日中は穏やかで、しっかりとした受け答えができる人だった。少し昔のことと現在が混ざるようなところはあるが、それもまた彼女の優しさを感じさせる部分でもあった。
「オムツが気持ち悪いの」
声は少しかすれていたが、しっかり聞き取れた。私はケア用品を持って、彼女の部屋へ向かった。
部屋に入ると、Tさんはすでに目を開けて私を待っていた。布団はきちんとかけてあり、彼女はにこっと笑って「ごめんね、夜中に」と言った。
「いえいえ、大丈夫ですよ。今きれいにしましょうね」
私は微笑みながら作業を始めた。
思わぬ一言
交換が終わり、布団をかけ直そうとしたそのときだった。
彼女が、ふと私をじっと見つめて、ぽつりとつぶやいた。
「その子、あんたの子かい?」
……え?
聞き返す前に、Tさんはさらに言葉を続けた。
「ほら、あんたの横に、ちっちゃい子がおるじゃろ? ずっと立って、あんたのこと見とるよ。あの子、あんたの子じゃないんかね?」

私は一瞬、呼吸を忘れた。
思わず肩越しに後ろを見たが、そこには誰もいない。部屋には私とTさんだけ。窓は閉まっていて、テレビも消えている。
「……いえ、私、子どもはいません」
そう答えると、Tさんは「そうかいね」と小さく笑い、ゆっくりと目を閉じた。
その瞬間、私は彼女の“視線”の残像を強烈に意識していた。
さっきまでの彼女は、確かに“何か”を目で追っていた。人を見つめる時の、あの真剣な、焦点の合った視線だった。
私は「おやすみなさい」と声をかけ、部屋を出た。
しかしその後も、背中に感じた何かが、廊下を歩くたびにじわじわと這い上がってくるようだった。
記録と証言に残る子どもの存在
翌朝、早番のスタッフにこの出来事を話すと、「Tさん、前から“子ども”の話しよるよ」と返ってきた。
「私のときは、“泣いとるけえ、あやしてあげて”って言われた。……怖いというより、Tさん、本気で見えとるような目をしてた」
さらに別のスタッフも、「夜中にTさんの部屋から、“よしよし”って声が聞こえてたけど、本人は寝てたはず」と話していた。
私はTさんの記録をさかのぼって読んだ。
すると、「夜中に壁の方へ話しかけている」「誰かを膝に乗せて揺らしているような仕草」といった記述がいくつも残っていた。
自宅に帰っても消えない記憶
その日の夜勤が明け、自宅に戻っても、私は妙な違和感から抜け出せなかった。
寝ても寝ても疲れが取れず、ふとした瞬間に、あの夜のTさんの目線を思い出す。
夢にまで出てきた。
あの部屋で、Tさんがベッドの脇を指差している夢。
その先には、見たことのない子どもが、ただじっとこちらを見つめている――そんな夢だった。
目が覚めても、背中に汗がびっしょりだった。
📝 あとがき:認知症の“記憶の交差点”としての幻視
認知症のある方の中には、過去と現在の記憶が混ざり合い、まるで「今そこにあるかのように」過去の体験を再現することがあります。
それが時に、“幻視”や“独り言”という形で表れることがあります。
Tさんも、おそらく若いころに子育てを経験していたのでしょう。
その記憶が、夜の静かな時間に呼び起こされ、あたかも「そこにいる子ども」として再構成されていたのかもしれません。
ただ、それが一人の職員だけでなく、複数人が「Tさんが子どもに語りかけているように見えた」と証言するほどの“共通の現象”になると、単なる記憶の混同や幻視だけでは説明がつかない感覚が残ります。
介護の現場では、医学や科学では割り切れない「不思議な出来事」に出会うことがあります。
それをどう受け止めるかは人それぞれですが、私たちが大切にすべきなのは「その人が確かに感じたもの、見たものを否定しない姿勢」なのだと思います。
Tさんにとって、あの“子ども”は確かに存在していた。
それが幻か、記憶か、何か別のものだったのかは、もう誰にもわかりません。
でも、あのときTさんが見せた優しいまなざしと、「あんたの子かい?」と尋ねた声だけは、今でも私の中に鮮明に残っています。