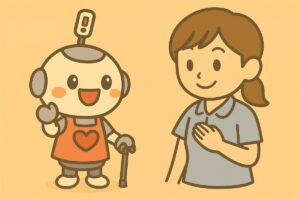深夜の静けさに響いた足音
グループホームでの夜勤中、いつも通りの見回りを終えて休憩に入ろうとしていた時だった。深夜2時。全ての利用者が就寝し、館内は静まり返っていた。空調の低いうなり声と時計の針の音だけが、遠くから聞こえてくる。
そんな中、廊下の先で小さな足音が響いた。
パタ、パタ、パタ……。

私は思わず顔を上げた。誰かが歩いている。足音のリズムからして、高齢者の歩き方ではない。勢いがあり、どこか若々しさを感じた。
廊下の照明は薄暗く、人影は見えなかった。私は身を起こして耳を澄ませ、再び足音がしないか確認した。けれど、それっきり何の音もしない。
「気のせい……かな」
自分に言い聞かせ、再び座ったが、胸の奥に不思議なざわつきが残っていた。
おばあちゃんが戻ってきた理由
それから30分ほど経った頃、今度はTさん(90代の利用者)が部屋から出てきて、トイレの方へ歩いていった。Tさんは夜間に何度かトイレに行くことがあり、そのたびに職員が付き添うようにしている。
「大丈夫ですか?付き添いますね」と声をかけようとしたその時、Tさんがトイレの前で立ち止まり、ドアノブに手をかけた。
カチャッ。
ドアがわずかに開いた瞬間――
バタンッ!
勢いよく扉を閉めたTさんは、顔色を変えてこちらへ戻ってきた。震える手、焦点の合わない瞳、そしてかすかに揺れる唇。
私は駆け寄って「どうされましたか?」と尋ねた。Tさんは少し怯えたように、小さな声でつぶやいた。
「兵隊さんが使ってた」
兵隊さん?
私は一瞬、言葉の意味が理解できなかった。
「え? 兵隊さん……?」
Tさんは、私の顔をしっかり見つめながら、さらに言葉を続けた。
「中にね、兵隊さんがいたんよ。帽子かぶって、ちゃんと制服着て。便器に座ってたけぇ、入れんかった」

私は背筋に冷たいものが走った。
「……誰もいませんでしたよ。中、確認してきますね」
勇気を振り絞ってトイレのドアを開けた。
誰もいない。便器も、床も、タイルも、ぴかぴかに掃除されている。
もちろん、帽子をかぶった“兵隊”などどこにもいない。
しかしその場に立った瞬間、微かに鼻を突くような鉄臭いにおいと、湿った空気がまとわりつく感覚がした。清掃の行き届いたはずの場所に漂う、説明できない違和感。
その夜、前例のない出来事だった
翌朝、早番のスタッフにこのことを伝えると、意外な言葉が返ってきた。
「えっ……兵隊さん? そんな話、聞いたことないよ……」
早番のスタッフは、目を丸くして驚いていた。
「私も長くここで働いてるけど、そんなことを言った利用者さん、初めてかも」
他のスタッフも思い当たる様子はなく、Tさんの“兵隊さん”の話は、どうやら初めてのケースだったようだ。
私は、また背筋がゾワリとした。
もし本当にそこに“兵隊さん”がいたとしたら……
Tさんの見たものは、幻ではなく、何か“残っていたもの”だったのだろうか。
あとがき:認知症の幻視、それとも…
認知症のある利用者が語る言葉の中には、ときおり「それは現実なのか?」「幻なのか?」と考えさせられるものがある。
幻視は、レビー小体型認知症などに顕著に見られるが、Tさんにはそうした診断はなかった。
ただ、記憶の層が重なり合い、現在と過去が混ざるような体験は、多くの認知症の方に共通して起こることがある。
また、利用者の経験や人生背景から来る幻視は、ときに強い印象と現実感を伴って現れる。Tさんは戦争を経験した世代でもあり、もしかするとどこかで見た記憶や情景が、深夜という静寂の中で具現化されたのかもしれない。
それでも今回のように、過去の記憶とも思えない“兵隊の姿”を語り、なおかつ前例のない体験として語られるというのは、偶然とも思えない。
科学的な根拠はない。
それでも、介護現場では時折、「本当にあったかもしれない不思議」が、静かに顔を出すのだ。
「兵隊さんが使ってた」――その一言は、Tさんだけではなく、私たち職員の心にも、忘れられない印象を残していった。