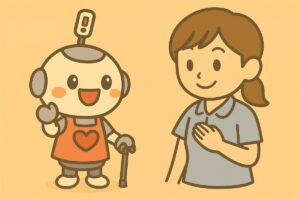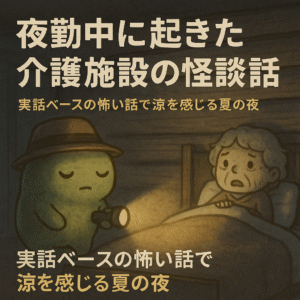認知症のAさんと向き合う日々 〜心を通わせるケアのかたち〜
私たちが認知症の方と関わる中で、もっとも大切にすべきものは何でしょうか? それは「人としての尊厳」と「安心できる環境」だと私は感じています。 この記事では、Aさんという一人の認知症を抱える方との日々の関わりから得た学びを通して、 認知症ケアの本質に触れていきたいと思います。
ある日常の中のAさん
Aさんは80代の女性。穏やかな表情と芯のある性格が印象的な方です。 しかし、認知症の影響からか、自分が今どこにいるのかがわからなくなることもあり、 ときには「家に帰らせて」と涙ながらに訴える日もあります。
初めてAさんと関わったとき、私は戸惑いました。 「どう声をかければ安心してもらえるのか?」「帰宅願望をどう受け止めればいいのか?」 そんな疑問ばかりが頭を巡っていました。
否定せず、受け止める
ある日、Aさんが「もう遅いから帰らないと…家で猫が待っとるけぇ」と不安げに訴えてきました。 そのとき私は、「今は少しだけここでゆっくりして、猫ちゃんの話を聞かせてください」と返しました。 するとAさんは「うちの子はね、三毛猫でな…」と表情が緩み、話し続けてくれました。
その瞬間、私は気づきました。 帰宅願望の裏にあるのは「大切なものを守りたい」という強い思い。 それを否定せず、そっと受け止めるだけで、心の距離がぐっと縮まるのです。
変化はゆるやかに、確かに
最初は日に何度も帰宅を訴え、不安な表情が多かったAさん。 けれど、安心できる関係性が少しずつ築かれるにつれ、表情に変化が現れてきました。
笑顔の回数が増え、スタッフや他の利用者さんに「ありがとう」と言う場面が増えたのです。 もちろん、日によって不穏な状態になることもあります。 けれど、その波の中にも「信頼」が積み重なっていることが、日々の表情や言葉にあらわれていました。
小さな気づきが生む、大きな意味
認知症ケアには「正解」はありません。 マニュアル通りにはいかない毎日の中で、私たちができることは、 一つひとつの言葉、表情、動作に「気づき」を持つことです。
「今日は朝の表情が柔らかいな」「声かけに対して、目が合ったな」 そんな小さなサインの積み重ねが、Aさんにとっての「安心」へとつながっていきました。
認知症の先にある「その人らしさ」
認知症は「記憶がなくなる病気」ではなく、「記憶をたどる道が見えにくくなる状態」だと感じます。 Aさんは、今でも季節の話になると昔の思い出をぽつりぽつりと語ってくれます。
「子どもの頃は、夏は川でよう泳いどったんよ」 そんな話から、今の季節を意識できるような活動につなげることもできました。
「その人らしさ」は、失われてはいません。 ただ、取り出す方法を私たちが一緒に探していくだけなのです。
私たちができること
認知症ケアにおいて必要なのは、「治そうとすること」ではなく「寄り添い、共に過ごすこと」。 Aさんとの関わりから、私はその大切さを何度も実感しました。
忙しい日々の中でも、立ち止まって耳を傾ける。 正面からではなく、斜め横に座って目線を合わせる。 その小さな工夫が、信頼関係を育んでいく土台になります。
おわりに
Aさんとの関わりを通して私が学んだこと。 それは、「認知症であっても、人は人として、心を通わせることができる」ということです。
認知症という言葉にとらわれず、Aさんの「今この瞬間」に向き合うこと。 その積み重ねが、よりよいケア、より豊かな生活につながっていくのだと信じています。
私たちができることはまだまだたくさんあります。 Aさんのように、毎日を懸命に生きている方々に、これからも心から寄り添っていきたい。 それが、私の願いです。